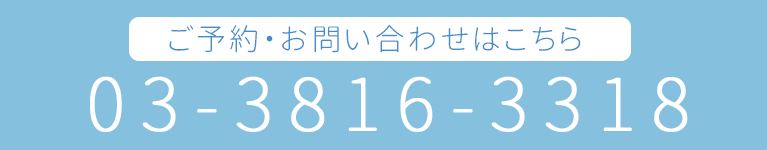メッセージ
このページでは院長 高橋秀実からのメッセージを掲載致します。
- 脂質制御医学の到来に向けて:東洋医学の智慧に学ぶ(2018年3月18日、平成30年度 同門会誌)
- 真理からの誘い(2017年3月18日、平成29年度 同門会誌)
- 研究の醍醐味(2016年3月18日、平成28年度 同門会誌)
- 生体制御システムを解除する医薬の時代に向けて(2015年3月18日、平成27年度 同門会誌)
- STAP細胞とCopy & Paste(コピペ)文化(2014年3月18日、平成26年度 同門会誌)
- 未曾有の高齢化社会(2013年3月18日、平成25年度 同門会誌)
- 念ずれば通ず(2012年3月18日、平成24年度 同門会誌)
- Positive Thinkingのすすめ(2011年3月18日、平成23年度 同門会誌)
- 古代人の智慧(2010年3月13日、平成22年度 同門会誌)
- 暗黒からの脱出:神のお導き(2009年3月25日、平成21年度 同門会誌)
- 漢方と自然免疫(2008年4月18日、平成20年度 同門会誌)
- 母との別れ(2007年3月20日、平成19年度 同門会誌)
- エイズ再考(2006年3月18日、平成18年度 同門会誌)
- 東洋医学への回帰(2005年3月8日、平成17年度 同門会誌)
- 文献からではなく現場から学べ(2004年3月18日、平成16年度 同門会誌)
- 弔辞(2003年2月9日、平成15年度 同門会誌)
脂質制御医学の到来に向けて:東洋医学の智慧に学ぶ(2018年3月18日、平成30年度 同門会誌)
平成29年11月12日(日)、本学同窓会館(橘桜会館)で開催された日本東洋医学会東京 都部会において、大会長として発表した際のメイン・テーマは、「漢方薬の本質的な作用機 序はどのようなことであろうか」ということであった。塾考した結果得られた、「脂質制御 医学の到来に向けて」という視点は、おそらく今後の免疫学を考える上で、非常に大切な考え方となるであろうことから、この場を借りて再度考えてみたい。 我々は、飲食物を介して体内に三大栄養素、すなわち「脂質」、「糖質」、「蛋白質」とともに 「微量調節因子」である「ビタミン群」や、「ミネラル」を体内に取り込み、生命活動を維持 するためそれらを利用後、不用となった産物を「排尿」、「排便」活動を介して体外に排泄し ている。こうした生命活動を維持する上で漢方薬の作用機序を新たに考えてみた場合、陰陽 五行説における生体に具わっている五腑、すなわち「胃」、「胆嚢」、「小腸」、「大腸」、「膀胱」 といった栄養素の吸収・排泄に関る粘膜で覆われた管腔臓器に着目した場合、その存在意義 は以下の様に捉えることができる。 口腔内に取り込んだ飲食物は、咀嚼することによって、まず唾液中に含まれるアミラーゼに より、エネルギー源である「糖質」が分解され、その分解産物は食道を介して「胃」内に運 搬される。そして、胃内に送りこまれた食餌成分は、塩酸の存在下で胃液中の消化酵素ペプ シンにより、その中に含有されたタンパク質が分解される。その結果、糖質・タンパク質が 分解してされ、胃液中に残った成分の主体は脂質となる。こうして胃酸の中に溶け込んだ脂 質は胃の幽門を通り、十二指腸のVater乳頭部に達し、そこで放出されたコレステロールを 主体としたアルカリ性脂質である胆汁酸により中和されるとともに、膵液リパーゼにより分 解される。こうして各種の酵素群により消化分解された飲食物は十二指腸を通過し、非常に 長い道のりである小腸としての空腸、回腸に運搬される。そこで、水溶性のアミノ酸、糖質 は小腸の静脈を経由して、また脂質群は乳び管を介して吸収され、身体に必要な様々な要素 となる。こうして、多くの水溶性栄養素は血中に脂溶性栄養素は腸管内に入り体内利用され るものの、小腸で吸収されず不要となった物質及び非水溶性物質群(その主体は脂質群と考 えられる)は、回盲部から大腸に入り、排泄過程に入る。大腸に移行した排泄様物質のうち 水溶性部分は腸循環を介して膀胱に向かい尿として排泄され、残った脂質はその運搬を担う 大腸菌の菌体表面に定着し大腸菌とともに体外に排泄される。それ故、グラム陰性桿菌とし ての大腸菌の表面は、多糖体脂質であるLPSに覆われているのである。以上より、様々な栄 養素は、その吸収・分解の過程で、体内を巡る「胃」、「胆嚢」、「小腸」、「大腸」、そして「膀 胱」といった管腔臓器、すなわち「腑」の粘膜面における脂質汚染を惹起する、と考えられる。翻って考えてみるに、このような「五腑」における脂質汚染こそが、図1に示す様な対応する「五 臓」の機能低下を惹起する原因ならば、「腑」における汚染に関わる脂質(糖脂質)の洗浄・ 除去こそが、治療の主体となるべきであろう。およそ2,000年前に構築された「漢方医学」は、 こうした観点から導かれた医学であると推測される。例えば、漢方薬の「柴胡」、「甘草」、「人 参」など種々の薬草に含まれた「サポニン」群は語源は「シャボン」と同義であり、この「サ ポニン」群を多用して来たのが東洋の医学である。この東洋の医学は、同時に脂汚れが付き にくくするものとして、薄荷、桂枝、丁子、茴香(ウイキョウ)などの精油群(アロマオイル) や、γδ型T細胞などの皮膚粘膜における修復機能を活性化する玉露の成分であるテアニン や、紫外線や抗癌剤などによる細胞破壊酸化作用を抑制する抗酸化作用を有するフラボノイ ドなどを多用する。また、こうした脂質群が、我々の自己治癒力を根底で支える「樹状細胞群」は、これらの脂質群を捕捉提示し、自己治癒力の実行部隊である「NKT(natural killer T) 細胞」や、「γδ型T細胞」を活性化するする「CD1分子群」を、その表面に発現している こと、さらにはこの「CD1分子群」を介して脂質抗原によって樹状細胞群が制御されている ことも明らかとなってきた。換言すれば、脂質によって我々の防衛システム、あるいは自己 治癒力が統御されている実態が少しずつ明らかとなってきたのである。 こうした科学の進歩は、時代遅れの医学、非科学的な医学と蔑まれて来た東洋の医学の重 要性を再認識させてくれるものと期待したい。多くの疾病と闘い、自己を修復するための医 学の中で、脂質医学の重要性が再認識される日は近い。
真理からの誘い(2017年3月18日、平成29年度 同門会誌)
微生物学免疫学教室の主任教授を1997年に拝命してから、早いもので20年の歳月が流れ た。この間、多数の大学院生、教室員とともに多岐にわたる研究を進めてきたが、そうした 研究にも一応のピリオドを打たねばならない時期が迫ってきた。その一つのまとめとして、 昨年夏8月21日から26日までオーストラリア国メルボルン市で開催された第16回国際免 疫学会議で8題の演題発表を行った。その内容は、HIV感染に関するもの、ピロリ菌に関す るもの、アレルギーに関するもの、生殖免疫に関するもの及び腫瘍免疫に関するものであっ たが、そのうち7題がシンポジウムならびにミニシンポジウムに口頭発表として採択された。 これまで、幾度となく国際免疫学会に演題を提出してきたが、このように多数の演題が口頭 発表となったことは初めてであった。特に大学院生にとっては、ハイレベルの国際免疫学会での英語での口頭発表は初めての経験であり、その準備は大変であったと思われる。しかし ながら、みなそれぞれが英語での発表のみならず、たどたどしいながら英語での質問に英語 で答えることができ、大変良い経験を積むことができた。私が担当する最後の国際免疫学会 議が、こうした思い出に残るものとなり、有終の美を飾ることができたことに心より感謝し たい。さらに今回発表した内容の多くは、抄録提出後に論文としてまとめ上げられ、現在次々 と一流国際誌に受理されている。大学院での研究生活は大変であったと思うが、このような 中で真理にふれることを通じ研究の醍醐味を味わってくれたならば、望外の喜びである。我々 を取り巻く自然界は、本当に謎に満ちており、その謎を解く過程で教科書には書かれていな い多くの真実を学ぶことこそが、患者さんを救うための「愛と研究心」をもった医師・医学 者となるためには非常に重要なことと思われる。 私自身これまで多くの患者さんに出会ってきたが、その中で強く感ずることは、様々な病 は表面的には医療者が治癒を手助けすることもあるが、本質的には病を患っている患者さん の中に内在する「自己治癒力」によって病から解放される、ということである。この治癒力 を生涯をかけて学び続けることが医師の宿命なのであろう。その意味で、医療者は人間を造 られた神の存在を感じながら、日常活動を続けていくべきものであり、私もそのような過程 で多くのことを学んできたが、こうした活動に加え、研究活動を通じ自然界の真理にふれる ことは自身の生長に繋がるものであることを強く感ずる。その意味で、医療者は「愛と研究心」 を持ち続けなければならない。こうした中で、優秀な職員や大学院生とともに、医療を通じ 多くのことを患者さんから学び、研究を通じて真理を学ぶことができ、本当に有り難いと感 じている。 翻って考えるに、オーストラリアでの国際免疫学会議を振り返り、強く印象に残った ことがある。学会最終日の8月26日金曜日、Richard Flavell, Vijay Kuchroo, Antonio Lanzavecchia 3名の世界的な教授が、各分野のまとめと今後の展望について語られたが、そ の際共通して述べられたことは、様々な疾病と樹状細胞との関連であった。樹状細胞を発見 されたSteinman教授はもうこの世にはおられないが、先生が残された樹状細胞に関する様々 な知見は、いま新たな医学を生み出す原動力となり、今後多くの疾病を解決していく礎とな ることを3名の教授の話から確信した次第である。今、私自身は研究生活の最終コーナーを 曲がったところで、ずっと考えてきた丸山ワクチンの作用機序解明にこの樹状細胞が強く関 与することを感じている。多くの患者さんを診る中で黙々と研究をされ、誰にでも謙虚に頭 を垂れられた腰の低い丸山先生は、残念ながらご存命中には評価を受けることはなかったが、 その重要性を強く感ずる。先生の偉大な発見を世に知らしめるためにも、私自身に大学での 残された時間は僅かであるが、真理からの誘 いざないにひかれ、もう少し頑張ってみようと思う。
研究の醍醐味(2016年3月18日、平成28年度 同門会誌)
研究生活を長年続けていると、自然界のからくりの一端を垣間見るというのが研究の醍醐 味であることを時折感ずる。私にとって、その一つの時期が研究者としてのスタートを切っ た米国NIH留学中及び帰国して研究者としての道を切った時であり、またもう一つの時期が 教授職について20年以上が経過し定年を目前にした現在であるのかも知れない。 米国に渡り、キラーT細胞やヘルパーT細胞などの獲得免疫担当細胞の認識抗原が、タ ンパク質の切れ端としてのペプチド断片であり、そのペプチドを構成するアミノ酸一つ一つ がT細胞レセプターによって認識されていることを、自身が合成したペプチドを用いて確認 出来た時には鳥肌が立つほどの驚きを覚え、その詳細な内容がJEM誌ならびに書評ととも にScience誌に掲載された時は研究者としての醍醐味を感じた。こうした研究の内容をもと に、帰国後も研究を続けた結果、更なる発展を遂げ、その集大成は再度Scienceに掲載され ることとなった。 またNIHでの最後の研究として、樹皮より抽出したサポニンを基に構築されたISCOMと いう物質に遭遇したが、このことが私にとってその後の新たな研究の起爆剤となった。従 来、「細胞外から捕捉された抗原断片は断片化され抗原提示分子であるクラス II MHC分子 を介して細胞表面に提示され、その断片はヘルパーT細胞によって認識されるのに対し、癌 抗原やウイルス抗原のように細胞内で産生された抗原は、断片化されクラス I MHC分子と ともに細胞表面に提示されキラーT細胞によって認識される」ということが免疫学の大原則 があったが、このISCOMを用いた研究の成果は、その大原則の変更を余儀なくさせるもの であった。すなわち、蛋白抗原をISCOMとともに接種すると、「断片化されたペプチドはク ラス I MHC分子とともに細胞表面に提示されキラーT細胞を活性化させる」という現象を 発見することとなった。この研究は私の後任としてNIHに招聘した産婦人科学教室の竹下 俊行教授にお手伝い戴き、帰国後に完成することが出来たものであるが、嬉しいことにこの 研究の内容はNature誌に掲載され、私が提唱した新たな免疫学の概念は「fresh pathway」 としてNature誌の“News and Views”でも大きく取り上げられた。その後、この「fresh pathway」を有する細胞が、樹状細胞という白血球1万個に1個程度の細胞の一部でありそ の表面にDEC-205という分子が発現した樹状細胞であることが解明されるとともに、「fresh pathway」は「cross-presentation」という新たな概念となって現在に至っている。規定の概 念をひっくり返すような研究は、過去の文献に基づいた研究からは決して生まれることはな く、そのような新たな概念に遭遇することもまた研究の醍醐味である。 最近になり、このDEC陽性樹状細胞は、体内の免疫動態を細胞性免疫優位、すなわち Th1優位の状態にシフトさせる作用を有しており、抗体産生を主体とした体液性免疫、すな わちTh2が優位の病態の改善に資することを見いだした。一般に、IgEを介し花粉などの特 異抗原に感作されたマスト細胞は、特異抗原に出会った場合ヒスタミンを遊離し様々なアレ ルギー症状を誘発するが、このヒスタミンの放出を抑制するのがDEC-205陽性樹状細胞であ ることを発見した。この事実は、例え抗原特異的なIgEを大量に保持する体質であっても、 体内のDEC-205陽性樹状細胞を選択的に活性化することで、様々なアレルギー疾患が制御可 能であることを物語っている。研究の詳細は後に述べることにするが、驚くべきことに、我々 は結核菌抽出物である丸山ワクチンがこのDEC-205陽性樹状細胞を選択的に活性化する能力 を有することを見いだした。恐らく丸山ワクチンは、DEC-205陽性樹状細胞の選択的活性化 を介し、腫瘍だけでなく様々なアレルギー疾患の制御にも有用な効果を持っているのであろう。 一方において、我々はNKT細胞の選択的な活性化能を有した多糖体脂質、αガラクトシ ルセラミド(α-GalCer)もまた、DEC-205陽性樹状細胞を選択的に活性化させる能力を有することを発見した。また、Th2優位の妊娠状態に、α-GalCerを投与するとDEC-205陽性 樹状細胞が活性化され、妊娠状態が中断され流産が引き起こされること、そしてその流産の 発生には妊娠子宮の筋層内の活性化NKT細胞が強く関与すること、さらには先天的にこの NKT細胞を欠損しているマウスでは、いくらα-GalCerを投与しても流産が誘発されないこ とを見いだした。 さらには、エイズ患者において現在最も有効な抗ウイルス剤による治療(HAART)をし ても、治療の中断により速やかに血液中にウイルスが出現してしまうことから、HAART治 療を行い、全く血液中からウイルス粒子が消失した状態のHIV感染者の小腸粘膜生検組織を 調べたところ、粘膜内に棲息するCD4分子を有したVα24陽性NKT細胞にHIV粒子が潜 伏感染しており、現在のHAART治療ではNKT細胞内のHIVは制御されないことが確認 された。HAART治療を長年に亘り継続している患者において、消化管粘膜を主体に難治性 の発癌が認められることが報告されているが、これは粘膜に棲息するNKT細胞の長期に亘 るダメージが原因であることを示唆している。こうした結果より、HIV感染は血液中のCD4 陽性T細胞が主たる感染標的であり、そのダメージがAIDSの病態であると考え治療薬の開 発を進めてきたが、実際の主たる感染表的はCD4陽性T細胞ではなく、CD4陽性NKT細 胞では無いであろうかとの仮説を立て、研究を展開している。CD4陽性Vα24陽性NKT 細胞はTh1型であり、そのダメージはウイルスや結核菌に対する抵抗力を落とすのに対し、 CD4陽性T細胞のダメージはTh1及びTh2双方の免疫力の低下を誘発する。しかしながら、 AIDSの病態では明らかにTh1が選択的に障害されている。こうした事実を無視し、HIVの 感染標的はCD4陽性T細胞であって、誰もCD4陽性Vα24陽性NKT細胞であるとは言 及しない。真の病態は今後の解明に待つとして、CD4陽性NKT細胞に対するHIV感染の重 要性に関しては、今後も研究を進めて行きたい。 以上、微生物学免疫学教室を主宰してからおよそ20年の歳月が流れ、この間様々な研究 成果が得られたが、この数年間は樹状細胞、NKT細胞など自然免疫に関する研究に取り組 み、各種の疾患に関する新たな病態が露呈し、その本体に迫る多くの予想外の結果が得られ ている。残された時間、研究の醍醐味を求めて、さらに教室員、大学院生、研究生らとともに、 邁進していく所存である。
生体制御システムを解除する医薬の時代に向けて(2015年3月18日、平成27年度 同門会誌)
私たちの体内には、生体反応が過剰とならないように種々の抑制システムが配置されてい る。例えば、生体が取り込んだエネルギーをできるだけ失わないために、腎臓の糸球体で一 旦老廃物とともに排泄された過剰な糖分は、近位尿細管を介して再吸収するようになってい る。これは、たとえインスリンの作用不良によって高血糖になった糖尿病の患者であったと しても同様で、この再吸収のお蔭で再び高い血糖値が保持される。この尿細管による糖の再 吸収を担っているのが、「ナトリウム・グルコース共役輸送体2(sodium glucose transporter 2 : SGLT2)」というタンパク質である。従来より、SGLT2の作用を阻害すれば、尿細管での ブドウ糖の再吸収が抑制され、血糖値が下がることが指摘されてきたが、この阻害によって 尿中には過剰な糖が常に放出され、尿路感染などが誘発される可能性が高まることも知られ ていた。このSGLT2阻害剤が医療の中で使用され、糖尿病のコントロールを担う時代が訪 れた。その結果、血液中の過剰な糖分は膀胱を介して体外に排泄され、血管病であった糖尿病の病態は大きく変化するものと予想される。すなわち、飢餓に苦しんだ人類が獲得した糖 の保持機能が、高栄養の現代人には悪影響を及ぼし不要であるとの見地から、SGLT2阻害薬 が現代に登場し、今後の治療に使用されていく時代を迎えたと考えられる。このような、生 体機能を阻止、抑制させることが我々にどのような影響をもたらすのか、今後の長期的な検 証が待たれる。 また、飲食物や防腐剤、あるいは様々な薬物とともに血液中に蓄積された血糖や脂質、あ るいは多量の老廃物が、血管を通じて急速に他の臓器に流れていかないようにするため、血 管壁には血管壁を収縮させ血流阻害を誘発するアンギオテンシンⅡレセプター(AT2R)が 配置されている。肝臓や脂肪細胞から分泌されたアンギオテンシンノゲンより誘導・変換さ れたアンギオテンシンⅡは、このAT2Rに結合することにより血管の収縮を促し、血液中の 物質の急速な移動を阻害する。その結果、血管の受ける圧力の上昇、すなわち血圧の上昇が 引き起こされる。おそらくこうした昇圧システムは、元来急速な血液中の老廃物の流入を阻 害することにより、流入先の臓器を保護するために、血管壁に配置されたものであったと推 察されるが、このシステムをAT2Rの応答を阻止する薬剤、すなわちAT2R-ブロッカー(ARB) の薬剤の登場によって、血圧の上昇を抑えることができるようになった。現在、血管拡張剤 であるカルシウム拮抗剤とともに、このARBが最も広く使用されているが、はたしてこう した薬剤の長期使用が、各臓器に良い影響を与えるか否かに関しても長期的な観察が必要で あろう。また、こうした血流速度抑制システムによる血圧の上昇が認められている患者にお いて、血液成分自体が汚染されている可能性についても考慮する必要があろう。 このように、生体に内在する様々な制御システムが、時に各種の病態を誘発することが判 明し、それらの制御システムの作動を抑制する医療が次々と展開されてきているが、本年よ り実際に本邦でも実用化された、癌患者における免疫制御システムをストップする抗体医薬 の意義について紹介し、諸氏とともに考えてみたい。 従来、体内にできた腫瘍細胞は、免疫監視システムから逃避したものであるから、癌患者 において腫瘍細胞そのものを破壊・排除する免疫力はなく、従って腫瘍は外科的に切除する か、抗癌剤あるいは放射線によって直接に除去するしかない、という考えが癌治療の主体で あった。ところが最近、癌に冒され末期となった患者においても癌細胞を制御するための免 疫システムが存在し、それが患者の体内で抑制されていることが明らかとなってきた。その 結果、この抑制力、すなわち抗腫瘍免疫に対するブレーキをはずした場合、従来使用されて きた様々な抗癌剤を遙かに凌ぐ抗腫瘍効果、延命効果が認められることが明らかとなってき た。これまで免疫学が解き明かしてきたように、実際に腫瘍細胞を破壊・排除する主役は、 腫瘍細胞特異的なキラーT細胞(cytotoxic T lymphocytes : CTL)であり、このCTL誘導 の鍵を握るのが樹状細胞(私は特にDEC-205分子を発現した腫瘍内樹状細胞と考えている) であると考えられる。次ページの図に示したように、樹状細胞がCTLを活性化する際、樹 状細胞上に発現した活性化共刺激因子であるCD80、CD86の存在が非常に重要である。通 常活性化に際しては、CTLは自己に発現したCD28分子を介して共刺激分子からの刺激を受 け取るが、過剰な活性化を抑制するため、CTLの表面にはこの共刺激分子からの刺激を回避 するための分子であるCTLA-4が発現している。従って、CTLA-4からの刺激の入ったCTL は腫瘍細胞に対する傷害性を持たない。またこうした活性抑制能力をもった分子がCTL活 性化能を有した樹状細胞表面にも発現しており、その主体はPD-L1と呼ばれる。このPD-L1 は活性化したCTL上に発現したPD-1という分子に結合し、CTLの腫瘍細胞傷害性を抑制 する。このように、樹状細胞上にもCTL上にも、腫瘍化した自己細胞、或いはウイルスな どに感染した自己に対するCTLの過剰な応答性を制御するような制御システムが予め構築 されている。興味深いことに、腫瘍化した自己細胞の表面にもこのPD-L1分子が発現しているため、腫瘍細胞は攻撃を仕掛けてきた特異的CTLの傷害活性を、CTL表面に発現した PD-1分子を介して抑制することができる。近年の免疫学の進展は、PD-L1によるPD-1結合 を介したCTL活性の抑制、およびCTLA-4を介した共刺激分子からの抑制シグナルを回避 することによって、CTLによる抗腫瘍免疫が増強することを明らかにしてきた。以上の結果、 米国を中心として抗CTLA-4抗体、あるいは抗PD-1抗体、抗PD-L1抗体による抗腫瘍免疫 増強効果の研究が進められ、その有効性が従来の化学療法などを凌ぐ結果が報告されるに至 り、本邦でもこの1月から抗PD-1抗体による治療が、まずはメラノーマを対象疾患として 薬価収載された。すでに、抗PD-L1による治療も認可され抗CTLA-4抗体による治療も進め られている。 こうした治療の根幹には、腫瘍細胞に対する特異免疫が癌患者の中で誘導されているとい う、従来とは異なる概念がすでに浸透してきたことが前提となっている。このような中、抗 PD-1抗体を1年間投与した患者1名の薬価が、およそ1,500万円となることが明らかとなっ た。抗PD-L1抗体の年間投与額も1名あたりほぼ同様の1,500万円となる。また、上述した ように現在はメラノーマのみが保険診療の対象となっているが、米国での治験状態を鑑みる に、今後は肺癌や腎癌などにも使用されてゆく可能性が高い。また抗PD-1抗体ならびに抗 CTLA-4抗体の投与によるCTLの歯止めない活性化の結果、自己細胞が高頻度に破壊され自 己免疫疾患が高頻度に起こることも米国を中心に報告されている。 以上、現代医療が我々の体内に内在する様々な制御システム、ブレーキを排除することに よる様々な疾患の治療に向かっている現状を述べてみた。こうした医療はすべて高額化して おり、人智を集めたこれらの医療が、人類にとって吉となるのか、それとも凶となるのか、我々 は慎重に見守る必要があろう。
STAP細胞とCopy & Paste(コピペ)文化(2014年3月18日、平成26年度 同門会誌)
本年の科学分野を最も賑わせた話題の一つが「STAP細胞」である。1月30日付けの Nature誌によれば、マウスのある時期におけるリンパ球を弱酸性液に25分間浸したり、細 いガラス管を通す、あるいは両者を組み合わせることによって、様々な外部からの刺激を細 胞表面に与えると、細胞内の遺伝子が先祖返りをおこし、様々な細胞に分化する多能性細胞 STAP(Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency cells)となるとのことであった。こ れに対しノーベル書を受賞した山中教授のiPS細胞は、癌遺伝子c-Mycを含む4種類の遺伝 子をレトロウイルスベクターを用いてマウス繊維芽細胞に導入し誘導された、多能性を備え たES細胞(胚性幹細胞)に酷似した細胞のことを指している。これらの多能性細胞群は今 後の再生医療の実現の鍵を握るものとして多くの注目を集めている。 従来の概念からすると、細胞を他の機能を有した細胞に変化させる場合には、細胞内へ遺 伝子導入を行う必要があり、まさにその路線に沿って作成されたのがiPS細胞ということに なる。ただし、こうして細胞内に遺伝子導入をした結果誘発されてくる細胞は、ウイルスベ クターの遺伝子や発癌遺伝子なども含んでいるため、なかなか人体への応用に至るには時間 を要することが推察される。ところが、細胞表面を適正な形で刺激することによって、細胞 内の遺伝的変化が誘発され先祖返りが誘発できるとしたSTAP細胞は、より医療応用への実 現の可能性があると当初想定された。 筆者等は、体表面の皮膚や粘膜における免疫システムを研究する過程で、消化管粘膜の免 疫システムを刺激することによって、皮膚に移植した癌が消失する可能性を動物実験で見い だしており、体表面の刺激によって我々の体内は制御可能になるのではないかと考えていた。 これは、皮下に定期的に結核菌由来の物質を接種することによって、体内に発生した癌の制 御が可能であるとした丸山ワクチンの発想に類似する。さらには、ウイルス感染細胞内のウ イルス遺伝子の制御が、感染細胞表面のレセプター等を介した適切な刺激によって可能であ るとの知見も得られている。以上より、細胞あるいはその集合体である人間もまた、表面を 何らかの形で刺激することによって、内部の情報に影響を与え変化させることが可能である のかも知れない。このように考えていた矢先のSTAP細胞の発表は、私に大きな衝撃を与えた。しかしながら、その後のSTAP細胞にまつわる報道は、この興味深い仮説を根底から覆す ものであった。それは、こうした多能性細胞が遺伝子導入を必要とせず誘導可能であるか否 か、という以前の問題としてあまりにお粗末な状況に向かっているのが現状である。この発 表をした女性の未熟さに起因するとはいえ、このような研究者が、まじめに取り組んでいる 科学研究の世界に入り込んでしまう状況を、私は心より危惧している。 その一つの原因が、現在蔓延しているCopy & Paste文化(通称コピペ文化)である。こ の傾向は、インターネットが発達した現在、大学の実験レポートの報告、時には学位論文を 書く際にも横行していると推測される。すなわち、他人が書いた文章を、ネット上から取っ てきて、あたかも自分が書いたように組み合わせ、報告書を作成する文化である。こうした ことは、自己の発想、ならびに自己の成長を停止させ、やがては自分自身のものの見方、考 え方をも停止させる。その結果、科学者のみならず、恐らく人間として最も重要な能力であ る「閃き」が失われ、自分で実験し、そのデータの中から本質的なことを探り当てることが 出来なくなってくる。医療の世界でも、この自己発想としての「閃き」がどんどん欠如して きている気がする。医師にとって最も重要なことは、患者さん1人1人を観察し、その根底 で生じている現象を考えることである。他人が行った検査結果とそのコメントをみながら、 症状に合わせ薬を処方していくことでは無い。向き合った患者さんを詳細に観察し、そこか ら患者さんの中で起こっている事象を洞察し、経験を積むことである。この経験の積み重ね が、医師としての「閃き」を生むと考えられる。ところが、全神経を集中させこの観察や洞 察を何分間しても、予約診療における再診料が3割負担で200円程度に抑えられている現在 の保険医療制度では、残念ながら医師の質の向上は望むべくもないような気がする。 この「閃き」は、現実の中で、作業を続けることによってのみ養われるものであり、科学 者にとって最も必要なものである。他人の見解や表現を考えることなく受け入れるコピペ文 化は、自己発想を抑制し、国家の統制を敷くためには重要な事項であるかもしれないが、こ のコピペ文化から脱却し、自己の発想を涵養し、「閃き」を養うことこそが、現在の教育の 中で最も重要なことのように感ずる。
未曾有の高齢化社会(2013年3月18日、平成25年度 同門会誌)
3月10日(日)の夕刻に羽田を出発し、14日(木)の早朝に帰国するという2泊4日の 強行軍で、シンガポールにおいて開催された日米医学感染症部門会議へ出席・発表をして来 ました。今まで多くの国々へ参りましたが、シンガポールへ出かけるのは今回が初めてでし た。深夜11時半に羽田を離陸し軽く飲食をした後、午前1時頃眠りについてまもなく、明 け方4時前にキャビンアテンダント(CA)の方から「おはようございます」との声がかけ られ、顔を拭くための温かい濡れタオルを渡されました。それはまさに、救急病院などで当 直をしていたころ、突然電話で起こされた感触でした。胃腸は完全に休息に入っていたにも 関わらず、「お食事はどうなさいますか」との問いかけに夢中で返答し、取り敢えず出され た朝食を流し込み、一服したところで着陸の態勢に入り、早朝シンガポール空港に到着しま した。 入国審査を経て、同行していた国立感染症研究所の俣野先生ならびに東大医科研の立川先 生とタクシーに乗り、会議場であり宿泊場でもあったマンダリン・オリエンタルホテルに向 かいました。朝の7時過ぎに到着したため、チェックインは可能かと問い合わせたところ、 チェックインは午後になるとの返事でしたので、しばらくフロント脇のソファーに座って時 間をつぶしました。8時過ぎから会議が始まりましたが、全て英語で行われていたため、睡 眠不足のためか不覚にも一瞬気を失うような状況となり船を漕いでいたところを、後ろにい たシンガポール大学に移られ研究を続けられている山本直樹先生(東京医科歯科大学名誉教 授)から、「高橋先生睡眠学習ですか」と言われるはめになってしまいました。 何とか午前中の会議を乗り切り、久しぶりにお会いした日米会議の面々と、マンダリンホ テルに隣接した「Food Court(室内型屋台食堂)」に出かけ昼食をとることにしました。シ ンガポールという国家は華僑を中心とした中国人が7割程度を占め、それに英語を公用語と するインド人、フィリピン人が加わり、さらにタイやベトナム、マレーシア、日本などから アジア人が加わって構築された国際国家です。「Food Court」には中国料理、インド料理を 始め各種のエスニック料理、そして吉野家などが散見されましたが、その中心は中華料理で した。塩分などの味は日本人にとっては若干濃いめで、熱帯を反映してか、全体的に発汗し やすいように辛めに調理してある感じがしました。 日本とは異なり、食事を取るときには大声で話す者も多く、非常にnoisyな感じがし、20 数年前に立ち寄った上海の光景が脳裏をよぎりました。私の上海の印象は、非常にエネル ギッシュで人々の活力が至る所に充満していること、そしてこのエネルギーは個々の人々が 独自に発した統一性のないエゴを内包したものであり、自分さえよければ良いという協調性 を失ったものに変化するものである、ということでした。この方向性を失ったエネルギー は、自分を救済するために使われ、時には社会の統一を破壊するものとなるかも知れませ ん。こうした視点から、改めて食事を取っている人々を見渡した時、私はある種の戦慄を覚 えました。それは、60〜70歳を超えた老人の姿が、数百人が同時に食事を取っている「Food Court」の中に全く認められないことでした。 ホテルにいた日本人と思われる観光客の中に高齢者の姿がチラホラと認められましたが、 この「Food Court」に隣接したショッピングモールにも、ほとんど高齢者の姿は認められま せん。いったい、日本では当たり前に認められる高齢者の姿は何処へ行ってしまったのでしょ う。そういえば、きちんと整備された路上を歩く高齢者の姿もほとんど認められません。青 信号が点滅する時間は日本よりかなり短く、道路を横断する際には足早に渉るしかありませ ん。ゆっくりと歩いていては轢かれてしまう感じもしました。熱帯のためか、まだ3月とい うのに外気の温度は30度を超え、夕方には突然スコールが襲い、スコールが去った後には モワーっとした湿気が漂う状況でした。この中で、マラリヤやデング熱などの様々な感染症 が流行し、多くの人々の命が奪われていくのだと思います。高齢の方は、どこか山の方での んびり暮らしているのかも知れませんが、都会で暮らす人は非常に少なく、温暖で暮らしや すい日本に高齢者が多い理由も分かるような気がします。あらためて、人類が今まで経験し たことのない未曾有の高齢者ゾーンに日本が突入していることを実感しました。 現在、「アベノミクス」という言葉に煽動され、日本は円安、インフレの方向に向かって おります。これから突入する超高齢者社会において、日本は人為的な物価の上昇を引き起こ し、自動車や家電を主体とした多くの物質を海外に輸出することによって所得をさらに上昇 させ、より富んだ経済状態に向かうことが高齢者を主体とした国民の幸せに繋がるのでしょ うか。円安に伴う石油などの価格の上昇、様々な輸入製品価格の上昇が引き起こされる状況 で、収入が増加するとは思えない高齢者の生活はどうなるのでしょうか。一千兆円を超える 負債を抱え、年金も支払えなくなった政府にとって、お札をどんどん印刷し流通させることによって1万円の価値を下げ、高齢者が蓄えている資産の価値を下げ、経済活動を活発化さ せようとしています。 いま高齢者にとって必要なことは、高齢者の存在を感じないシンガポールのように自己の エネルギーによる活発な経済活動を促すよりも、将来の不安を払拭し、消費を刺激するより も、安心して日常を過ごせるような施策をとることだと思います。そのような中で、全身的 な機能低下を起こし様々な疾病に陥る高齢者は、抗生物質や抗癌剤、さらには高価な抗体医 薬などのピンポイントに作用する急性期治療の組み合わせを実施するよりも、身体の持って いる「自己治癒力」を維持し活性化するような医療の必要性を感じます。その意味で、自然 界のめぐみである「人参」、「生姜」、「紫蘇」、「柴胡」などの「生薬群」、ならびに自身のエネ ルギーの巡り司る「経絡」を利用した「鍼灸治療」を組み合わせた「ECOで安価」な医療で ある東洋医学的な医療、を現代医療に取り込むことも大切なことではないでしょうか。
念ずれば通ず(2012年3月18日、平成24年度 同門会誌)
昨年暮れの11月30日から12月2日までの3日間、新宿のホテル「ハイアット・リージェ ンシー東京」で「第25回日本エイズ学会学術集会・総会」を無事開催することができました。 参加者は総勢1,500名に達し、3日間延べ4,000〜4,500名に及ぶ方々にご参集を頂き、大変 実り多い会でありました。ご協力頂いた教室員ならびに関係各位に、この場をお借り致しま して厚く御礼を申しあげます。 さて、日本エイズ学会理事会において「第25回日本エイズ学会学術集会・総会」の会長 に選出されたのが平成21年6月でした。それから学会開催までに2年半の猶予がありまし たが、まずは会場選びでした。時間を見つけては、日本エイズ学会事務局の佐々木さんと一 緒に、あちこちのホテルやコンベンションを回り会場探しに取りかかりました。そして、会 場費を考慮しながら、学会期日の中に出来れば12月1日の「エイズデー」を盛り込みたい という考え、および私が評議員をやっております「第40回日本免疫学会学術集会」が平成 23年11月27日〜29日に千葉の幕張メッセで行われることがその数ヶ月前に決まっていた ため、会期を重複しない形で11月30日〜12月2日の3日間に設定し、候補会場を探しました。 まだ2年半あるから大丈夫と安易に考え、当然空いているだろうとの予測から、その時点で の第一候補であったリニューアルした麹町の「日本都市センターホテル」を訪ねましたとこ ろ、12月3日〜4日に「日本性感染症学会」が会議の予約をその前日の12月2日からと、 その数日前に済ませてしまったので12月2日はお貸しできない、とのことで佐々木さんと 一緒にかなりがっかりしたことを覚えております。その後、「京王プラザホテル」を含め幾 つかのホテル、あるいは「横浜パシフィコ」などをあたりましたが、どこも11月30日〜12月2日の3日間は予約で埋まっていたため、会期を変更することも考えました。 ところが、どうしようかと途方にくれていた際、これまでほとんど大きな学会場の会場と しては使用されていなかった、新宿の「ハイアット・リージェンシー東京」が借りられるか も知れないという情報が入り、早速佐々木さんとともに「ハイアット・リージェンシー東京」 に赴いたところ、会場担当の山口さんという方が会場となる各部屋を案内してくださいまし た。エレベーターを降りた地下1階に丁度手頃な部屋が7つあり、さらに幾つかの小会議を 開ける部屋が揃っていて、エイズ学会を開催するにまさに理想的な状況でした。問題は会期 です。平成23年の11月30日〜12月2日が空いていますかとの問いかけに対し、丁度一部 の結婚式の申し込みをする場所さえ残して頂ければ、地下1階全体が使用可能であるとのご 返事でした。さらに、学会の準備をするためとエイズ学会の理事会を開催するために前日の 11月29日の夕刻を使用できるか、との希望を全面的に了承して頂き、「地獄で仏」とはまさ にこのようなことを言うのであろうと強く感じた次第です。実際、山口さんの顔が「仏」に 見えました。学会が終了したところで、山口さんからお聞きした言葉ですが、山口さんも「是 非私の応援をしたい」とその時に感じたそうです。ただ、「ハイアット・リージェンシー東 京」は高級なホテルですので会場費が非常に高いことが危惧されましたが、それも最終日の 12月2日(金)の夜を他の宴会のために早く空けることで解決され、大変良心的な価格で会 を催すことができました。まさに「念ずれば通ず」です。 大変不思議なことですが、この「念ずれば通ず」という現象が今回の学会ではもう一つ 起こりました。それは、学会のメインゲストとしてオランダからお招きしたアムステル ダム大学のGeijtenbeek教授のことです。昨年のノーベル医学生理学賞を受賞したRalph Steinmann教授は樹状細胞の発見者として知られておりますが、Geijtenbeek教授はこの樹 状細胞上に非常にユニークな微生物捕捉因子であるDC-SIGNという分子が発現しているこ とを世界で初めて発見し、その結果ならびに関連事項を2000年にCellという雑誌に2編の 論文を筆頭者名で掲載し、一躍世界の注目を集めた方です。彼はその後もヒットを飛ばし続 け、2007年にはNature Medicine誌に表皮内に棲息する樹状細胞の1種であるランゲルハン ス細胞は、その下の基底膜より下部に存在する樹状細胞とは異なり、ランゲルハンス細胞に はランゲリンという分子が発現しているのに対し、樹状細胞にはランゲリンが発現しておら ず、DC-SIGNという分子が発現していることを証明するとともに、エイズウイルスを捕捉・ 消化する分子がランゲリンであり、エイズウイルス捕捉・伝播するのがDC-SIGNであるこ とを示しました。この発表に大変興味を覚えた私は、いつか機会があればGeijtenbeek教授 のお話を直接お聞きしてみたい、そしてとても無理だとは思いますが、できれば私の主宰す る日本エイズ学会で御講演頂きたいと願っておりました。会場が決まり、具体的な招待講演 者やプログラム委員を決めねばならない矢先、平成21年暮れに、ある1通のメールがスイ スから届きました。そこには、私に平成22年3月29日に、国際的な免疫学者らが集まるス イスのダボスで開催予定の、「第4回国際免疫制御学会」での樹状細胞に関する講演依頼の 知らせでした。私は、その時の大学院生8名とともに、この学会に参加することにし8編の 大学院生の抄録と私の抄録、合わせて9編の抄録を年末に大急ぎで取り纏めました。そして、 その講演者の中にGeijtenbeek教授の名前を見つけました。この学会は3月29日から4月1 日までの4日間開催される予定となっており、驚いたことに先生の講演時間は、私の講演と 同日の2時間ほど前でした。 残念ながら、その場では先生とゆっくりお話しすることができず、自己紹介をする程度で したので、帰国後メールを出そうと考えておりました。初日の平成22年3月29日の夜に大 半の大学院生のポスターセッションでの発表が終了し、翌日は発表が無かったため、3月30 日の昼からスイスで最も古い町クールへ出かけました。ところが、クールへ向かう列車で楽しく昼食をとろうとした矢先、昼食で皆と食べようと思い鶏の唐揚げを購入した際に、スー パーマーケットにパスポートを置き忘れてきたことに気付き、昼食どころではない状態に陥 りました。列車の乗務員にこのことを伝えたところ、次の駅で反対方向の列車にうまくすれ ば乗れるとの説明を受け、慌てて反対方向の列車に乗り、出発地点にとって帰りました。非 常に幸運なことに、スーパーで私のパスポートが見つかり、ホッと安堵した次第です。大 学院生らと話合った結果、とにかく1〜2時間遅れてしまったが、次の列車でクールに向 かうこととなり、再度列車に乗り込みました。列車が発車する少し前、見覚えのある大男 が私どもと同じ車輌に乗り込んで来ました。本当に驚きました。それはGeijtenbeek教授で した。彼も前日に自己紹介をした私の顔を覚えていたらしく、それからおよそ1時間程度、 Geijtenbeek教授とゆっくり列車の中で話をすることができました。この一連の奇跡的なこ とは、一緒にいた大学院生も見ております。 列車の中で、私は彼と旧知の仲ではないかと錯覚をするほど、彼と色々なことを話しまし た。彼はこれからチューリッヒ経由で米国に向かい講演をするとのことでした。彼が乗換駅 であるLandkartに到着する直前、私は次年度の11月末から12月初旬にかけて日本に来る ことができるか、と切り出しました。彼は、その時期ならば行くことが出来ると思うが、予 定を調べてみなければはっきりとは約束できない、お互いが母国に戻った時点でメールをす る、との言葉を残しLandkart駅で皆で記念撮影をし別れました。その彼が、本当に「第25 回日本エイズ学会」に姿を見せただけでなく、この同門会誌の写真に示すように、私どもの 教室に立ち寄り講演後、一緒に根津神社を散策した次第です。彼とは、現在共同研究を進め ています。 以上の話は全て真実で、そこには目撃者もいます。エイズ学会は、予想以上のできで大成 功でした。自分でもこんなにうまく行くとは思っていませんでした。何か、大きな力が働い ていたように思います。まさに「、念ずれば通ず」だと感じます。この大きな力を「絶対他力」 と呼ぶならば、この「他力」は、自分で誘導しようとしても無理であり、ただひたすら毎日 を謙虚に一生懸命に、感謝の気持ちを持って、生きることしかないように感じます。この世 には、私どもを動かす何かとてつもない大きな力があるような気がします。
Positive Thinkingのすすめ(2011年3月18日、平成23年度 同門会誌)
ちょうど1週間前の3月11日(金)の午後3時頃、学生の再試験の採点を大学の自室で していたところ、机がガタガタと振動し出しこれまでに経験したこともないような大きな揺 れを感じた。通常の地震とは異なり、揺れている時間がとてつもなく長く感じられた。隣接 したカンファレンスルームに行ったところ、すでに大勢の職員が目を皿のようにしてテレ ビの画面に見入っていたが、そこで目にしたものは、地面を這うようにして家屋をなぎ倒し ている「地震に伴う巨大津波」の光景であった。それは、以前観た、確か「The Day After Tomorrow」という米国映画の恐ろしい情景と重なっていた。この映画は、地球温暖化によっ て南極の氷山が溶け出し海水の増量に伴って突然訪れた竜巻や津波のリアルな映像が主体で あったが、それと酷似したテレビの映像が現実のものであることを確認し、強い戦慄を覚えた。 結局この津波は「東北太平洋岸から関東へと続く」広域の巨大地震によるものであること が判明し、驚くべきことにマグニチュードは本邦における観測史上初めての9.0を提示し、 震源地からかなり離れた東京でも震度5強を記録した。この震災のため東京の交通機関は全 面的に麻痺状態となり、多くの人が徒歩で自宅へ帰ることとなった。また地震に伴う火事や 津波で家屋を失う者も多く、各地の避難所は辛うじて助かった人々の呻吟が充満していた。 悲劇はそれでは終わらず、翌12日には福島における原子力発電所で白煙が立ちのぼり、予 想されたことではあったが、放射能の漏出が始まった。地獄の始まりの幕開けとも言える情 景であった。 こうした震災と放射能漏出の中、日本の株価は急落し円高が進行するとともに、外国人は この国を離れ、母国や隣国に逃げ出した。また数日のうちに、外国人投資家による株式を始 め預貯金も大量に流出していった。こうして「世界で最も安全で住みやすい国」ともてはや された我が国は、一瞬にして世界で最も危険な国に転落した。さらにそれに伴い、原子力発 電に依存してきた東京電力からの電力供給が著しく低下するとともに、熱源・エネルギー源 である石油・灯油が枯渇し、物資ならびに人民の輸送が困難となり、人々は飢えと寒さに直 面することになった。まさに「この世の地獄」が人々の希望を絶望に塗り替えた。このよう な状況下において人々は、次に起こるであろう事象を否定的に捉えるような心情に陥る。そ して、その負の想念(Negative Thinking)が、さらなる負の事象をより加速的に展開するこ とになり、心に芽生えた生きる希望を消滅させていく。その際重要なのは、目の前に起こる 事象に対する否定的な想念を捨て、自己を取り囲むより大きな力に身を委ね肯定的に捉える 思考、Positive Thinkingに切り替えてみることである。 自分に起こる様々な事象は、自分を成長させより豊かなものの考え方を生んでゆくための神様からの贈り物であるかも知れないと考えることである。そのような思考の結果、現状を 冷静に認識しより素晴らしい人生を見いだすことになる可能性は十分にある。「暗黒の中に 光明を見いだす」ことこそが自己が成長するための重要なステップであるとすれば、今回の 想定外の試練は今後の自己の成長に繋がる大きな試金石といえる。 私が最も尊敬する弘法大師「空海」は、「生まれ生まれ生まれて生の始めに暗し、死に死 に死に死にて死の終わりに冥し(くらし)」と、私達が生まれ育っているこの現世は一寸先 が闇の「暗黒」の世であり、死に続くあの世は現世より少し明るく先が見える「冥土」であ ると喝破した。私は、この「暗黒の中に光明を見いだす」ための最も重要な思考方法の一つが、 冥土への道案内である神に従うこと、すなわち現状を己の成長のために神が作った「場」と 考え肯定する「Positive Thinking」ではないかと思う。否定的な想念が満ちあふれ、人々が「自 分さえ良ければ良い」と自己中心的な考えに陥る中で、あえて「Positive Thinking」により こうした現状を肯定し、損得の概念を超えて自らの成長を目指し精一杯生きることで、始め てこの難局を乗り越えられる可能性が出現するものと考えられる。神が我が国に投下したこ の試金石により、これからの日本が多くの国家から尊敬される国家に成長するかそれとも破 滅に向かうかは、その中に住む人民の考え方と行動によるものと考えられる。これから最も 重要な考え方は、否定的な想念を持ち現状から逃避し退廃的になることではなく、現状をあ りのままに見つめそれが自らを成長させる試金石と肯定する「Positive Thinking」であろう。
古代人の智慧(2010年3月13日、平成22年度 同門会誌)
我々の体内には一度体内に侵入した「疫」、すなわち各種「流行性伝染病」を惹起する病 原因子である「外邪(邪気)」の形状を記憶し、その再度の侵入に備える防御システムが存 在し、古来よりこの「疫」から免れるシステムを「免疫」と呼んできた。そしてこの記憶を有した「免疫」力を、「疫」の原因である「病原体」全体あるいはその一部を用いて予め体 内に刻み込む媒体が「ワクチン」であり、「ワクチン」によって天然痘やポリオを始め、様々 な重篤感染症を予防できることが「免疫」という言葉の持つ意味であった。今から2000年 以上前の中国古代の医学書であった「黄帝内径」の中にも「疫」という言葉、そしてその「疫」 から免れる「免疫」という概念が記されていたが、その時点における「免疫」の意味は果た して現代の「免疫」と同じ概念であったであろうか。 古代中国より発した中国医学(以下「中医学」と呼ぶ)では、「疫」の原因である様々な 病原因子である「邪気」の侵入を防衛する機構を「衛気」と呼び、この「衛気」は体表面の 皮膚・粘膜に存在すると考えられていた。上述した「黄帝内径」には、この「衛気」が充実 している状態に通常の「邪気」が侵入した場合には「邪気」は速やかに「衛気」に取り囲ま れ駆逐されてしまうため様々な症状を伴う発病はしないが、強い「邪気」が侵入した場合に は「衛気」との熾烈な戦闘が繰り広げられるため様々な病的現象が誘発される、と記載され ている。このように、一度も出会ったことの無い様々な「疫」の侵入を、体内に構築された 防衛システムが防御しうることが指摘されてきた。私は以前より、この初回侵入の際にも「疫」 を制御することのできる「衛気」こそが「免疫」防御システムの本体であり、その一部の機 能が「記憶」形成能を有する狭義の「免疫」システムではないかと考えてきた。 1990年代後半になって人類は漸く、我々の体表面には記憶を持たないにも関わらず、侵入 した病原体を識別しそれらを排除するための防衛システムが巧妙に構築されていることに気 付き、それを「自然免疫(innate immunity)」システムと命名し、従来の記憶を有する免疫 システムを「獲得免疫(acquired immunity)」と呼んで双方を区別するに至った。21世紀に 入り、この「自然免疫」システムを構成する樹状細胞群やマクロファージ、B細胞群等が、 その表面や細胞内に発現した異物認識レセプターであるToll-like receptors(TLRs)を介して、 侵入異物の形状をその表面を構築する細胞由来のリポ多糖体(LPS)、ペプチドグリカン(PG)、 リポアラビノマンナン(LAM)、あるいは鞭毛や繊毛などの特殊な構造分子パターンや、ウ イルスの複製あるいは破壊産物であるRNAを主体とした核酸群の構造を基に選別判定する ことが解き明かされていった。 この「自然免疫」システムにおいて中心的役割を担う「樹状細胞」は、侵入異物の情報を キャッチした後、自らに発現した個特異的な抗原提示分子であるMHC分子を介して異物の 構造情報をペプチド断片として提示し、MHC分子からの情報を認知するヘルパーならびに キラーT細胞群に特異的なレセプターの発現を促し、異物抗原情報を記憶定着させることに よって「獲得免疫」システムを構築する。このMHC分子を介した情報提示はMHC分子の 異なるT細胞群に対しては認知されないため、侵入異物構造に対する特異的な「獲得免疫」 は他人の樹状細胞によって誘発されることはない。 一方において、「樹状細胞」はもう一つの抗原提示分子群であるクラスⅠMHC分子に酷 似した構造を有するCD1分子群を発現しており、異物の侵入をキャッチした場合、これら CD1分子群を介して強い異物破壊能を有するナチュラルキラーT(NKT)細胞群やγδ型 T細胞群を活性化させるとともに、インターフェロン、TNF-α、IL-6などの放出を介して ナチュラルキラー(NK)細胞や、マクロファージ等を活性化させ、局所防衛力を高め侵入 異物の排除にあたる。 こうした「自然免疫」の機能ならびにネットワークの活性化、そして「獲得免疫」への抗 原情報の焼き付けこそが、「衛気」における「外邪」との闘いの本体であるならば、こうし たことを2000年以上前に喝破した、古代中国人の智慧には感服せざるを得ない。また、彼 らが洞察した「衛気」と「邪気」との熾烈な戦闘状態は、まさにウイルスや細菌群の持続感 染に類似した病態を示唆している。これら外邪由来の脂質や核酸群によってTLR群が持続的に刺激され、「自然免疫」を構築する樹状細胞、マクロファージ等から放出されたインター フェロン、TNF-α、IL-6等の作用に起因する様々な疾病が、慢性関節リウマチ、SLE、尋 常性乾癬などの難病を惹起することが明らかとなってきた現在、現代医療は放出された個々 のサイトカインの作用抑制に目を奪われ、高価な薬剤群の盲目的な使用に向かっているが、 この「自然免疫」システムそのものを制御活性化させることを念頭においた、東洋医学の智 慧に学ぶことは多い。
暗黒からの脱出:神のお導き(2009年3月25日、平成21年度 同門会誌)
米国におけるサブプライム・ローンの破綻に端を発した未曾有の経済危機は、瞬く間に世 界を席巻し、僅か数ヶ月にして夥しい失業者を世界中に生み出した。我が国でも派遣労働者 を中心に失業の嵐が吹き荒れ、多くの人々が路頭に迷う状態となっている。こうした派遣労 働者の解雇を行っている企業の主体は、これまで我が国の輸出産業を牽引して来た「自動車 産業」および「家電産業」であり、本邦が「もの造り国家」として世界中から一目置かれて いた分野である。世界を吹き荒れる不況の嵐は、盤石と考えられていたこれら輸出産業の勢 いを完全にストップし、ものを造っても全く売れない状況を構築している。その結果、人々 は人間として最低限の生活だけは確保するため、衣食住に要する以外のお金を浪費しない方 向へと向かっている。 こうした消費倹約の流れとは逆行する形で、経済消費は国家を養う血流との考えから、政 府は国民から集めた税金の一部を一時給付金としてバラマキ、幹線道路にかけていた通行料 を減らすことによって、人々の移動を促進し無駄使いをさせようと努力はしているものの、 将来への不安を抱えた国民は、一夜の夢と消えてしまうような金銭の使い方をせず、配布さ れた僅かな金額を貯蓄へ回してしまう状況が予想され、益々血流障害の状況に陥ってくる感 がある。この血流障害を改善するために先ずなすべきことは、将来への不安を取り除くこと であり、国民が安心して進める方向を指し示すことであろう。国家計略の羅針盤を失った状 況では、現在の暗黒の荒れ狂う海を渡っていくことは不可能であり、神の荒波を沈めるため の生け贄として、経済の専門家の意見に従い皆から集めた税金を投入しても、その程度の金 額では神の怒りは癒えず、全く光明は見いだせないでいるのが実状である。 私の尊敬する弘法大師・空海は、こうした人間界の状況を「生まれ生まれ生まれて、生の 始めに暗し」と、この世に生を受けた人間は生まれてからずっと真っ暗闇の中で生き、明日 をも予見できない中で自分自身の生きる方向性を模索せざるを得ない宿命にあると喝破する とともに、「死に死に死にて、死の終わりに冥し」と、我々人間は暗黒な「この世」での修 行の結果到達した死が間際となった「あの世(冥土)」へ向かう時になって、やっとほんの り明るく行く先が見えてくると言い放った。冥土とは、暗黒の闇が晴れ、ほんのり明るく浮 き上がった世界のことを指している。こうした暗黒は人間が相互に助け合うことを忘れ、私 利私欲をめざし個人的な欲望を満たすことに専念し始めた時さらに助長されるという。人間 が作り上げた実体と乖離した架空の世界(バブル)の中で非生産的なマネーゲームを続け財力を獲得していった結果、バブルの崩壊が招来され現在の状態に至ったのは予想されたこと ではあったが、人類の無知とエゴとが個人的な利益の追求を許容し暗黒の状況に拍車をかけ、 善悪を含め全く先が見えない盲目な状態に追い込んでいったとも考えられる。 実際我々はずっと米国及びそれに追従した識者と呼ばれる道先案内が示す方向に従い、世 界は一つというかけ声の下、「グローバルゼーション」という耳障りの良い言葉に酔いしれ、 盲目的に経済、文化、そして生活形態の画一化の中に光明があるものと信じてきた。 翻って現在おかれている医療の現状を見た場合、米国Centrocore社が開発した非常に高価 な薬剤としてのTNF-αの選択的阻害剤であるマウスモノクローナル抗体(レミケード)の 血管内投与が、夢の新薬として慢性関節リウマチ患者に対し爆発的に使用されているが、こ の薬剤によって関節痛は軽減されるものの治療の中止が可能となることは極少数例に限られ るという。ワンショット13万円という薬剤を最低1ヶ月に1〜2回投与しなければならな い現状は、現在の医療経済の状況では早晩破綻がくることが予想される。同様に、夥しい数 の高価な「標的治療薬」と呼ばれる抗腫瘍薬が、認可をめざして列をなしているものの、その 中には腫瘍を完治させるものは見出されておらず、あくまでも一時しのぎに過ぎないものが並 んでいる。慢性関節リウマチや癌が慢性疾患であることを考慮した場合、こうした高価な薬剤 の継続的使用は医療バブルを起こし、やがては医療の経済的破壊に繋がることが予想される。 人類は石油の発見によって新たな時代を迎えその先には明るい未来が待っていると教え込 まれて来たが、暗黒において自分たちの見いだした石油の炎を、この世を照らす太陽の光と 勘違いしてきた感がある。そこには冥土ではなくさらなる暗黒の世界が広がっており、全く 先が見えないにも関わらず煤けた空気の中でマネーゲームに明け暮れてきたのである。よう やくそのことに気付き始め、地球温暖化対策や自然保護の対策をうち始めた矢先、マネーゲー ムの終点とも言うべき現在が訪れたとも言える。 もしこの世を治める神というものが存在するならば、現在の状況は決して悲観するにはあ たらない。バブルの崩壊とマネーゲーム、グローバルゼーション環境破壊、高価な合成薬剤 群と医療崩壊、などを通じて人類の愚かさを示し、これまでの方向をあらため我々人類を導 くための新たな進むべき道を提示してくれている気がする。弘法大師空海は、我々の心の中 に内在する「自我の成長」が、直感力を高め進むべき方向を示す「光明」になると語っている。 「家族や自分さえ良ければ良い」という自己中心的な考えから、損得を離れ他人を支えること、 他への依存から自立することが自分自身の成長に繋がることを自覚し、我々の進むべき道を 感じ取ることの出来る善悪の判断ができる覚醒した人間がこの世に育っていくことを強く念 ずる次第である。現在の失業の嵐が、人々が自らがこの世に生を受けてなすべき「天職」に 付くための神の与えた神風となり、その中で覚醒した人々がこの暗黒の世に光明を放ち、よ り良い世の中が形成されていくことを期待したい。
漢方と自然免疫(2008年4月18日、平成20年度 同門会誌)
東洋医学科の部長を拝命してから2年間が過ぎた。大学院生の時に東洋医学に興味をもっ てからのことであるから、すでに27〜28年の歳月この医学を学び続けていることになる。 この間、どうして生薬が様々な疾病をコントロールできるのかあれこれと考え続けてはい たが、色々と思いつくことはあっても正解からはほど遠いところを彷徨い続けていたように思う。ただ、今から考えると、留学中の米国で最後に行い帰国後の1990年にNature誌に 掲載された仕事が、東洋医学の作用機序を解明するための一助となっているような気がし て、今更ながら人生の不思議さを感ずる。その仕事とは、樹皮から採取した配糖体である Quillaja Saponariaという物質をもとに作成された免疫賦活物質(ISCOMs:immuno-stimulating complex)とともにウイルス抗原蛋白を皮内免疫すると、通常は抗原特異的な抗体やそれを 補助するクラスⅡMHC分子に拘束されたCD4分子陽性のヘルパーT細胞が誘導されてく るはずであるのが、実際にはクラスⅠMHC分子に拘束されたCD8分子陽性のキラーT細 胞であるという発見である。 その後こうした結果は、クラスⅠMHC分子上にウイルスペプチド抗原をパルスした樹状 細胞を用いて免疫した場合に得られることが明らかとなった。このことは、樹状細胞がウイ ルス蛋白を取り込み、それを細胞内で断片化した後にクラスⅠMHC分子上に提示すること を示唆している。通常、細胞外から散り込んだ蛋白抗原は細胞内で分解されクラスⅡMHC 分子によって細胞表面に提示され、抗体産生を補助するCD4分子を発現したヘルパーT細 胞を活性化するが、樹皮から採取した配糖体(サポニン)と共に接種した場合には、抗原を 取り込んだ樹状細胞上のクラスⅡMHC分子ではなくクラスⅠMHC分子から抗原が提示さ れると考えられる。 この際、皮内接種ではなく筋肉内や腹腔内に同様のISCOMsと蛋白抗原を接種しても、ま た通常の免疫賦活物質であるフロイント完全アジュバント(CFA)や、それから死菌を除い たフロイント不完全アジュバント(IFA)などと共に接種してもキラーT細胞は全く誘導さ れなかった。このことは、体表面の免疫システム、ことにその中心に位置するランゲルハン ス細胞などの樹状細胞群が、サポニン系配糖体によってその抗原提示能を含め何らかの影響 を受けることを示唆している。このサポニンは脂質の除去あるいは修飾を行うシャボンの一 種とも考えられ、柴胡サポニン、人参サポニン、甘草サポニンなど多くの漢方薬に含まれて いる成分である。ISCOMsを用いた実験は、これらサポニン群が免疫系の司令塔とも言うべ き樹状細胞群の機能に影響を及ぼすことを暗示している。そして、様々なサポニン群を組み 合わせた漢方薬の経口投与は、まさに体表面に棲息する樹状細胞群の応答性に影響を及ぼす ものと考えられる。 昨年12月のImmunolgy Review誌にこうした体表面の樹状細胞の応答性が、様々な病態 を誘発するきっかけとなることが報告された。その樹状細胞の表面には、体内に侵入した異 物としての脂質やRNAを主体とした核酸群に応答するtoll-like receptor(TLR)と呼ばれる レセプターが発現しており、異物に反応し異物を除去するための様々なサイトカインが適量 放出される。しかしながら異物が持続的に産生・放出された場合には、これらサイトカイン は過剰放出され制御不能となる。こうした状況が各種の病態を作り出すと言うのである。例 えば、樹状細胞より過剰かつ持続的にTNF-αというサイトカインが放出された場合には、 このTNF-αに対するレセプターを発現した破骨細胞が恒常的に刺激され、関節局所におい て骨破壊が進行する。この病態が慢性関節リウマチなのである。現在、このTNF-αに直接 結合しその作用を抑制するエタネルセプトや破骨細胞上のTNF-αに対するレセプターをブ ロックするレミケードという薬剤が、画期的な抗リウマチ薬として使用され始めているのは 周知の通りである。しかしながら、これらの薬剤をいくら使用しても異物である脂質や核酸 群が除去されない限り、樹状細胞からのTNF-αの放出は止むことがない。従って、TNFαの作用をブロックすることと同時に、脂質や核酸群を除去すること、そして過剰に応答す る樹状細胞の機能を正常化することをしなければ真の病態改善には繋がらないであろう。ま さに、この真の病態改善に作用するのが、漢方薬に含まれるサポニン系の成分であるのかも 知れない。これまで人類の目は、体内に構築された抗体産生や様々な細胞群の放出するサイトカイン など遺伝子産物である蛋白抗原を主体とした獲得免疫の制御に向けられてきた。しかしなが ら様々な病態を引き起こす原因が、それら獲得免疫系を制御する体表面に構築された樹状細 胞群を司令塔とした自然免疫系であること、そしてこの自然免疫系が脂質およびRNAを主 体とした核酸群によって活性化される事実が明らかになってきた現在、脂質・核酸群を制御 する医学の展開は新たな治療への道を開くものと考えられる。こうした中、古来より使用さ れてきた、サポニン、精油、あるいはカテキン、タンニン、テアニンなどの生薬由来物質の 経口投与を主体とした東洋の智慧は今後益々重要な意味を持っていくものと推察される。
母との別れ(2007年3月20日、平成19年度 同門会誌)
母が本年2月20日早朝に亡くなり1ヶ月が過ぎた。母の遺志により近親者のみの密葬を行っ た。時々おそってくる漠然とした悲しみに誘われ、線香に火を付け、手を合わせる。線香の 煙と香りが鼻腔を通じ身体に吸い込まれていくに伴い、写真の中の母が様々な言葉を語りか けてくる。 丁度1年前、昨年2月下旬、風邪で近くのかかりつけの医院で診てもらっているが、何とな く微熱が出てお腹が張り苦しいとの電話があり、虫の知らせとでもいうのであろうか、2月25 日(土)夜7時30分頃実家を訪れた。元来元気であり、これまで1度も入院などをしたこと の無い母であったが、予想外に衰弱している様子であった。腹部の所見から腹膜炎症状が疑わ れたため、同日夜11時頃に私の外勤先である練馬の病院に転送し、常勤医との相談の上直ち に抗生物質の投与と点滴による補液を開始し、週明けの月曜日まで様子を見ることとした。 週明けの2月27日(月)、朝一番にCTスキャンによる腹部撮影と血液検査を行い、その 写真を大学に転送させ放射線科の田島教授同席のもと読影した。腹水貯留とともに卵巣部位 の異常陰影が認められたため、卵巣癌のマーカーであるCA125を含め数種の腫瘍マーカー を調べ、同日同門の産婦人科の竹下教授に相談し、日本医科大学付属病院への転院の手続きを取った。翌々日3月1日(水)、転院後直ちに腹水穿刺を行ったところ予想された通り血 性で、癌性腹膜炎を強く疑い、緊急で戻ってきたCA125の数値は1,500を越えていた。産婦 人科の検査はもとより、MRI検査、腎機能、肺機能、胃ファイバースコープを含めた消化管 検査、そして麻酔薬に対する感受性検査などを急いで実施し、3月7日(火)に手術を施行 することとなった。竹下教授のご厚意により、私も手術に立ち会い現状を知ることとなった。 直腸壁、膀胱壁への腫瘍の浸潤が認められており、子宮、および両側卵巣、そして大網の全 摘がなされた。後遺症の発生を懸念した私の希望を考慮して戴き、浸潤部位のリンパ節や腫 瘍塊の細部に亘る隔清は行わず、そのまま閉腹し手術を終え抗癌剤及び免疫療法としての丸 山ワクチンの投与に一縷の望みをかけることとした。 幸いなことに病理組織検査の結果、抗癌剤としてタキソールとカルボプラチンの併用療法 が有効である可能性が判明したので、術後3週目の3月27日(月)に抗癌剤1クール目を 実施した。術後バルーン抜去後尿閉状態に陥り全く自力排尿が出来なくなり、膀胱収縮剤な どが全く効かない状態に加え300cc以上の残尿が出現するようになってきた。祈るような気 持ちで針治療を連日実施したところ、開始後10日目頃になり尿意とともに自力での排尿が 可能な状態となった。連日のカテーテルによる導尿から解放された母のこの時の喜びようは なかった。以降母の希望もあり、入院中はほぼ連日、退院後も出来るだけ頻回に鍼治療を続 けることとなった。 その後、同様の抗癌剤を3クール実施後、骨髄抑制による白血球減少や脱毛などは起こった ものの、経過は比較的順調で5月20日に無事軽快退院となった。退院時のチェックでは、CT や超音波検査による腫瘍塊や腹水は全く認められず、CA125の値も10と完全に正常化してい たため、母の希望もあり退院後はしばらく私の家で鍼治療や丸山ワクチン投与を含め様子をみ ることとした。病状が安定し元気にもなってきたため、6月中旬から世田谷の自宅に戻ること となった。その後定期的に私の家に泊まり、そこから大学に通院し経過をみることとなった。 残念ながら再発の時期は思ったより早く訪れた。7月中旬の検査ではCA125の値も10以 下であり、安心していた矢先のことであった。8月中旬の大学の定期検査で腹部腫瘤の存在 が認められたため、8月下旬CTスキャンによる検査を行い、腹水貯留及びCA125の上昇が 確認された。竹下教授からの説明では、卵巣腫瘍の再発であり放置をすれば1,2ヶ月の内 に通過障害のため食事がとれず致死的な状態になることを告げられた。残された手段は前回 有効であった抗癌剤(タキソールとカルボプラチンの併用療法)を試してみることであった が、その効果については再発が早すぎるため断言出来ないとのコメントであった。 9月19日から4ヶ月ぶりの再入院となった。この時既に腫瘍塊の直径は15cmに達してお りCA125も361に上昇し、腹水貯留に伴い腹痛や排便困難な状況に陥っていた。幸いなこ とに再入院後3クール目(総計6クール目)が終了した時点で腹水も著明に減少し、排便や 排ガスもスムーズとなりCA125も240となったため、体重が10キロほど痩せ筋力はかなり 低下してしまったが、11月4日に退院となった。 その後7クール目の抗癌剤を投与したものの、12月上旬より腹水の貯留量も増加してきた。 最早抗癌剤によるコントロールはあまり期待できない状況であった。腹水などのコントロー ルを目的として、12月15日より再入院させアルブミンなどの補給や利尿剤の使用を実施し たが、次第に腹水とともに胸水(血性)も貯留して参り軽度の呼吸苦も訴えるようになった。 絶望的な状況ではあったが、先生方や看護師さんによる献身的な介護に加え、連日の鍼灸治 療・漢方薬なども奏功し、次第に摂食量も増え、年末には何とか自力で動けトイレにも行け る状態にまで回復した。当初は年を越すのは絶対に無理と言われていたが、せめて1月2日 の82歳の誕生日を自宅で迎えさせてあげたいとの気持ちから、酸素の設備と電動ベットを 用意し年末12月30日退院し自宅に連れて帰った。無事誕生日を家族に囲まれ迎えることができ母は嬉しそうであったが、その後の衰弱が激しく母の希望もあったため1月6日より再 入院をすることとなった。 入院後母は少し安心したようで、若干摂食量も増え貧血状態もHb5.8から6.8まで輸血を せずに改善していった。ただ、この頃より癌の悪液質に伴う凝固亢進状態であるDICの傾向 が進み、1月11日のFDPは168に達していた。恐れていた通り、1月19日に左下肢の血栓 が生じ著明な浮腫が誘発されたため、血栓溶解剤の使用およびカテーテルによる血栓除去術 の施行が考慮されたが、比較的血性腹水・血性胸水量が減っており状況が安定していたこと、 そして再出血による悪化を懸念し鍼治療と下肢の浮腫に対するマッサージ療法を併用したと ころ、下肢の浮腫はかなり軽減していった。また、1月末車椅子で院内を散策に行き喜んで いた矢先、今度はエコノミー症候群とも言える肺塞栓状態となり、15リットルの酸素投与に よっても酸素飽和度が60%程度にしか上昇しないため、緊急処置として気管挿管を実施する 状況下となったが、信じられないことに主治医の見ている前で数本打った鍼が奏功したのか 塞栓症状が改善し事なきを得た。これは私にとっても驚きの経験であった。この危機的状況 を乗り切った後、酸素を1・2リットル程度で100%近い酸素飽和度を維持することができる ようになり、以後亡くなるまで呼吸苦を訴えることはなかった。 それから亡くなるまでのおよそ3〜4週間は、ほとんど苦痛を訴えることはなく、比較的 安定した時期で、病院食に加えて父や家内らが持参したトロの刺身やアイスクリームや果物 そして様々なスープなどを美味しいと食べるようになり、毎日の鍼灸とマッサージ治療を楽 しみにしていた。私も出来る限り時間を見つけて母のもとに参り、食事の介護に加え時には オムツ交換や摘便を看護師さんと一緒に行った。この時期仕事を終えた後、母が休むまで付 き添うことが多かったが「、明日も来てね。待ってる。」というのが毎日の就寝前の言葉であっ た。亡くなる1週間前より次第にものの飲み込みが悪くなってきたため細心の注意を払って 食事をさせていたが、2月19日午前中いつものように鍼とマッサージを実施し「気持ちが良 い。また後で来てね。」との言葉を最後に、午後3時の回診時に突然意識障害と呼吸困難が 認められ、次第に呼吸量が減少し、翌2月20日午前1時37分息をひきとった。 手術、尿閉、抗癌剤治療による白血球減少、免疫不全、癌性腹膜炎、血性腹水、血性胸水、 DIC、左下肢血栓症、肺塞栓など多くの致死的な病態を母は乗り切ってきた。不思議なことに、 最後にはほとんど治療らしきものはしなかったにもかかわらず、母は最後まで自分の好きな 物を「美味しい」といって食べ、最後まで癌特有の痛みを訴えることはなく、そのためモル ヒネを含む鎮痛剤を一切使用することなく、最後まで自力での排尿・排便をし、正常な意識 を持ち続けたまま息を引き取った。そして「自分の人生に思い残すことはないよ」と時ある ごとに私に語りかけた。そして最後まで身をもって私に色々なことを教えてくれた。合掌。
エイズ再考(2006年3月18日、平成18年度 同門会誌)
1981年にGottliebという医師が後天性免疫不全症候群(AIDS : acquired immune deficiency syndrome:エイズ)という疾患の存在をNew England Journal誌に発表してか ら25年の歳月が経過した。初めてこの報告者の名前である「神(Gott)の愛(Lieb)」を耳 にした時は、実に不思議な印象を持ったことを記憶している。多くの先進諸国においては予 防啓蒙活動の普及に伴い新たな感染者の出現は減少傾向にあるものの、中国やインド、そし てアフリカ諸国などの発展途上国における感染爆発は継続しており、全世界における総感染 者数及び新たな感染者数も未だ増加傾向にある。実際、2005年度現在で4,000万人を越える HIV感染者が全世界に存在し、昨年1年間で約50万人の母児感染者を含む500万人の新た な感染者が世界中で誕生している。また、この25年間にすでに2,500万人の命が奪われ、昨 年のエイズによる死亡者数300万人を上回ることが報告されている。翻って本邦の現状を見 ると、大変情けない話しではあるが我が国は先進諸国中での数少ないHIV感染者の増加国で あることが2005年のWHO報告に記載されている。このような現状であるにもかかわらず、 相変わらずエイズは日本において忌み嫌われる疾病の最右翼に置かれ、感染症を専門とする 駒込病院や国立医療センターを除けば、都内での専門外来は殆ど無きに等しく、本学付属病院 においてもごく僅かな医師のボランティア活動により診療が続けられているのが実状である。 ただ、およそ10年前に始まった、逆転写酵素阻害剤と蛋白合成酵素阻害剤の組み合わせ による抗ウイルス療法(HAART療法)によりHIV感染による死亡者は激減しており、そ の意味でエイズは確かに不治の病ではなくなった。従って、多くのHIV感染者は外来通院に よる投薬治療で延命しているのが本邦の現状である。しかしながらこのHAART療法は非常 に高価であり、一人の患者に要する薬剤のコストは年間200〜400万円に及ぶため、その費 用が負担できる国家はごく限られている。また、薬剤に対する耐性が容易に獲得されてしま うため、常に耐性ウイルスの出現を遺伝子レベルでチェックすることが必要であり、変異ウ イルスに対し有効な薬剤に切り替えねばならないため、検査にもかなりの費用が必要となる。 更には、血液中のウイルス量を確実に減少させるためには薬剤の服用時間や量を厳密に守る 必要があるため、社会的な仕事をしながらではきちんと継続的な服薬をすることが困難とな る場合があり、自主的に服薬を中止せざるを得ないことも多い。このような場合、例え血液 中には全くHIVに感染したCD4陽性Tリンパ球が存在しなくなっていたとしても、それま で検出限界以下であった血液中のウイルス量は速やかに元のレベルに戻ってしまう。こうし たことは、ウイルスがどこかに潜んでおり、現在行われているHAART療法ではその根絶を することはできないことを示唆している。一体HAART療法により血液中から消えたHIV はどこに潜んだのであろうか。 このことに関する興味深い報告がある。今からおよそ10年前、アフリカのガンビアに HIVに対する感染抵抗性を獲得していると考えられる売春婦群の存在が報告された。この売 春婦群は、日常的にHIV感染者との性的接触を繰り返しているにも関わらず、HIVの感染 から守られているというのである。彼女らの体内にはHIV特異的なキラーT細胞の存在が 確認されたため、確かにウイルスの侵入を受けその複製・増殖を抑制するような免疫システ ムが明らかに構築されたと考えられた。また、彼女らの血液中からは全くHIVは検出されず 且つHIV特異的なIgG抗体も認められなかったことから、通常のHIV検査ではウイルスの 存在が確認できないものの、尿中からHIV特異的なIgA抗体が検出されたことから、HIV に対する細胞性免疫のみならず液性免疫も誘導されたものと想定され、以後HIV特異的なキ ラーT細胞と分泌型IgA抗体を誘導するようなワクチンの研究が進められた。しかしながら、 最近こうした感染抵抗性を獲得した売春婦群の追跡調査の結果が報告された。その結果は驚くべきものであった。売春婦群の中で結婚や家庭の事情などにより売春を中止したものの大 半で、血液中にHIVあるいはHIV特異的IgG抗体が検出されるようになり、HIVの感染状 態に陥ってしまったというのである。この事実は、HIVの何らかの成分が粘膜に侵入し、粘 膜免疫を恒常的に活性化させることによってHIV特異的なキラーT細胞の活性化やIgA抗体 の分泌が誘発され、その結果粘膜に潜伏していたHIVが制御されていたことを暗示している。 我々はこれまでの研究で、粘膜組織には比較的CD4陽性のTリンパ球が少ないこと、逆 に分泌型IgAに富む乳汁等の粘膜組織にはCD4陽性のマクロファージ・樹状細胞群に属す る抗原提示細胞群が多数存在すること、そしてこのようなCD4陽性マクロファージ・樹状細 胞群はHIVに対する感受性を有することを見出してきた。以上の結果をもとに、筆者は現在 HIVの真の標的は、従来考えられてきたように血液中のCD4陽性Tリンパ球ではなく、粘 膜組織中のCD4陽性マクロファージ・樹状細胞群、特に脂質抗原提示分子であるCD1分子 を発現したCD4陽性樹状細胞群ではないかと考えている。恐らく、この粘膜樹状細胞内に潜 伏したHIVがウイルスの長期に亘る保護細胞(reservoir)として存在し、血液中を巡回する CD4陽性Tリンパ球にウイルスを受け渡しているものと推測している。従って、HIVに感 染した樹状細胞を粘膜局所で制御することが重要ではないかと考え研究を進めている。残念 ながらこうした視点でエイズの征圧を考えている研究者は今のところ他には見当たらず、若 干独りよがりの所も否めないが、今暫くこうした方向で新たな治療法を模索して行きたいと 考えている。 HIVが「神の愛」によって世界に解き放たれたとするならば、その制圧をするなどという ことは大変おこがましく私などの手に負える代物ではないが、せめて神が放たれたウイルス がどのようにして我々に内在するシステムに影響を与えるのかを、曇りの無い眼で観察して 行ければと願いつつ研究を進めている。
東洋医学への回帰(2005年3月8日、平成17年度 同門会誌)
私が東洋医学へ興味を抱いたのは、丁度今から24〜25年ほど前、常岡健二先生率いる日 本医大付属病院第三内科学教室に入局し、医師としての研修を積んでいた頃のことであった と記憶している。当時GOT、GPT等の数値が高く肝生検による病理組織学的検査によって 原因不明の非A非B型肝炎と診断された患者さんの多くは、入院による食事と安静のみに よる経過観察を余儀無くされており、しびれをきらして退院することがよくあった。後にこ うした非A非B型肝炎の多くがC型肝炎ウイルスによって引き起こされたウイルス性肝炎 であることが判明し、その一部に対してインターフェロンの投与が有効であることが報告さ れるまでは、この慢性肝炎に対する有効な手立てはないのが実情であった。こうした患者さ んは、肝機能障害に伴い、全身倦怠感や食欲不振、下痢、胃部膨満感などの消化器症状を伴 うことが多く、これらの症状に対して消化剤や整腸剤などが処方されることが多かったが、 上述したようにウイルス性肝炎自体に対する特効薬はなかったため、GOT、GPT等の改善 は認められないまま退院し、付属病院あるいは近隣の関連病院で経過を観察するのが一般的 な流れであった。そのような中、アルバイトで行っていた病院で私自身が主治医を務めた非 A非B型の肝炎患者さんに久しぶりで出会うことがあった。その際、患者さんの状態が以前 に比べて良くなっており、肝機能の検査数値も著明に改善していたため、何か特殊な治療で も受けたのかと尋ねたところ、薬局で処方された漢方薬を服用しているとの返事が返ってき たのである。その時には、そのようなわけの分からない非科学的な薬が本当に効くはずがな いと思い、偶然に体調が良くなったのであろうと話し半分で2週間分の消化剤などを処方し て取りあえずお引き取りを願った。不思議なもので、その後その患者さんと極めて似たケー スに何例か出会い、漢方薬のことを少し学んでみたくなったのが東洋医学との出会いである。 丁度そのころ、大学院生として微生物学免疫学教室へ行くことになり、そこで当時主任教 授でいらっしゃった木村義民先生が「小青竜湯」の抗アレルギー作用の研究を、当時講師で あった竹内良夫先生とされていることを知るのである。どのような経緯であったか正確には 覚えていないが、竹内先生のところへ出入りしていた某漢方製薬メーカーの人に頼み込んで、 駒込あたりで開業されていた東洋医学の大御所の先生のところを紹介してもらったのが東洋 医学を学びはじめたきっかけであった。その先生は、まず漢方薬を学ぶためのバイブルとも 言うべき「傷寒論」の一節を良く読んで記憶することを指示された。ほとんど全く意味の分 からない漢文の内容をお経を唱えるように暗記する作業は私にとって非常な苦行であり、先 生には大変申し訳なかったが取りあえず挫折したように記憶している。それでも東洋医学を 学ぶことは諦めず、何か別の勉強法はないものかと再びメーカーの人に頼み込んだところ、 中国から来日している専門家を講師として定期的に東洋医学の勉強会が東長崎というところ で開かれているから、それに参加してはどうかとの返事があり、取りあえず参加したのが確 か「林春沢」という先生の講義であった。夜の8時からというのに、そこには診療を済まさ れた開業医の先生方や薬剤師あるいは鍼灸師の人たちが集まっており、非常に熱心に片言の 日本語や板書を駆使される林先生の講義に耳を傾けノートをとる光景に出くわした。こうし た江戸時代の寺子屋のような風景に胸を打たれ、自分も今度は諦めず少し勉強を続けていこ うと決めたのが本当の始まりであったような気がしている。そこに集まっておられた医師の 多くは開業されている高齢の先生方であり、研修医あがりの私は完全に異分子ではあったも のの、先生方は「今度の土曜日の午後、自分の診療を見に来ないか」、「先生は鍼灸には興味 がありますか」「面白い経過を辿った患者さんの話を聞かせるから遊びに来ないか」などの 暖かい言葉に従い、様々な経験を大学院生の間に積ませていただくことになったのは、非常 にラッキーであった。こうした中、私の東洋医学の芽を大きく育ててくれたのは木村義民先生であった。先生自 体も東洋医学には興味をお持ちであり、まだ東洋医学の使い手としてはかけ出しの私に、先 生御自身を始め、大切な奥様や御子息御夫妻、あるいはお孫さんの診療を依頼された。先生 の信頼を裏切ってはいけないと、一生懸命様々な文献をひも解き診療をさせて戴いたが、大 きな失敗もなく今考えてもビギナーズラックであると言えるようなケースに出会ったのは本 当に幸いであった。ある日の早朝、木村先生の奥様から電話があり、先生が突然激しい腰痛 に襲われベッドから起き上がれなくなったので見にきて欲しいとの連絡があり、先生の千石 の御自宅に馳せ参じたことがある。恐れを知らないということはこういうことを言うのであ ろうが、私は先生の脈拍や血圧が正常範囲であることから、針を用いた治療を試みたのであ る。天の助けとはこのようなことを指すのであろう。先生は私の針治療の後、無事起き上がっ て大学に向かわれることになるのである。今考えれば何と無謀なことをしたのかと、背筋が 寒くなる思いであるが、それ以降先生は私に東洋医学をもっと極めるようにとの指示を出さ れ、様々な患者さんを私に紹介された。この時の冷や汗の連続が、私の現在の東洋医学の基 盤を作ったものであることは間違いない。 楽しかった大学院での生活も終わり、古巣の第三内科に帰ろうとした時、私の卒業と同時 に主任教授から常務理事になられた木村先生から、もう少し教室で研究を続けてみないか、 そしてもう少し東洋医学の研鑽を積んだらどうかとのお話があった。さんざん迷った末、そ うした消化器病や内視鏡の修得を含め、臨床研修をしたいとの意向を先生にお話したところ、 平塚胃腸病院の平塚秀雄先生のところへ自ら出向かれ、4ヶ月程私は消化器の研修をするこ とになり、当時学長であられた常岡先生に掛け合って下さり微免の研究生として大学へ戻っ た後に毎週、内視鏡センターの実習生として内視鏡の技術を修得する機会を与えて下さった。 その間も自分なりには東洋医学の勉強を続けたが、昭和62年1月より米国に留学すること になり東洋医学の勉強は一時中断することになった。そして同年8月、木村先生御夫妻と ニューヨークの丘正道先生のお宅で再会した際、木村先生が常務理事を辞められ大学を去ら れたことを知ることになった。 その後大学に戻り、微生物学免疫学教室のスタッフとして研究・教育に携わることになっ たが、東洋医学との縁は消滅した。ただ、不思議なことに新しく始まった「自主学習」にお いて、東洋医学を免疫学の視点から見つめなおすテーマを取り上げたところ、予想外の学生 からの反応があり、再び東洋医学を学生とともに生薬の作用機序等も含め学ぶこととなった。 そして、自分自身も西洋医学と東洋医学とをドッキングさせたような医療をアルバイトの病 院で細々と行ってきたのがこれまでの経緯である。この間、1994年頃より「自主学習」の発 表会などにおいて、皮膚や粘膜などの体表面に存在するガンマ・デルタ型のT細胞を生薬や 鍼灸の「熱」エネルギーが活性化する可能性に関して言及してきたが、21世紀に入りハーバー ドのグループからお茶の成分のテアニンや、エネルギー体であるアルキルピロリン酸がガン マ・デルタ型のT細胞の活性化に関与するという衝撃的な発表に出会い、数年前より(株) ツムラから薬学に精通した人材を教室の研究生として招き生薬の真の作用の研究を始めてい た。こうした中、東洋医学科の部長を務められていた三浦先生が母校である東邦大学医学部 東洋医学科の教授として転出されることになり、旧知であった三浦先生からのご指名により 付属病院の東洋医学科の部長を兼務することとなった。木村先生が他界されてから2年、実 に不思議な巡り合わせによって私は東洋医学へ回帰することになった。きっとこのような展 開もまた天国からの木村先生の指示なのかもしれない。
文献からではなく現場から学べ(2004年3月18日、平成16年度 同門会誌)
日々の生活に追われる日常から僅かの間ではあるが解放され、自分自身を反省し考えを纏 めてみることは非常に重要である。慌ただしい中、そうした時間を提供してくれるのが毎年 3月に開催される日米医学会議であるのかも知れない。この会議は日本側と米国側が交互に 主催し、それぞれの国において歴史上重要な位置と考えられる場所において開催される。今 年は3月8日から10日まで、テネシー州のナッシュビル市というところで開かれた。我々 は元国立感染症研究所の部長で、数年前日本で行われた国際エイズ学会の会長を務められた 北村敬先生や元日本内科学会の理事長であられた木村哲先生ご夫妻らと、シカゴ経由でナッ シュビルに向かった。ナッシュビルの空港にホテルからの迎えの車が来るとのことであった ので、我々は根気よくその迎えを約1時間半待った結果、ホテルに到着したのは夜の10時 過ぎであった。もうレストランは終了していたため、バーかルームサービスでの夕食を余儀 なくされた。家を出発してから既に20時間程度を経過しており、時間の感覚は既になくなっ ていたが、我々はルームサービスでそれぞれの夕食を済ませることにした。12時近くになっ てからボーイが圧倒されるサイズのシーザーズサラダとスパゲッティを運んできたが、味は まあまあではあったものの、とても食べきれる量ではなく、飽食の国アメリカを再確認させ られた。この時点で、日本での時間の感覚はほとんど消滅しており、普段なら気になる1時 間程度の誤差は気にならなくなっていた。 翌日は、米国側の計らいで午後2時頃より貸し切りバスによるナッシュビル市の見学が入っ ていたため、早朝ならびに夕食後にびっしりと双方の発表がつまっており慌ただしい会議の スタートとなった。昼食のクラブハウスサンドイッチは、これまた量が多く半分程度しか食 べることができなかった。ナッシュビル市はカントリーウェスタン発祥の地であり、エルビス・プレスリーなどが隆盛を極めた場所として知られてはいるが、実はこの地には日本では あまり有名ではないものの、感染症研究で世界をリードしているVanderbilt大学がその中心 部に位置している。南北戦争の際、様々な感染症に苛まれた負傷兵を助けるために設立され たとのことであり、現在も多くの著名な感染症専門家がこの地より世界に向けて発信してい る。実際にVanderbilt大学の病院や研究施設を見学する機会を得たが、施設的には日本と同 程度であったものの、広大なキャンパスの中で人々は余裕をもって研究に取り組んでいる様 子であった。キャンパス内に足を踏み込んだ際、一瞬私自身が留学していたNIHに戻って来 たような錯覚に陥ったが、このVanderbilt大学のみならず多くの米国における大学は同様の 構築形態をとっているとのことであった。そして、このような基本的な構築を出来るだけ保 存しようとしているとの説明があった。 一見矛盾するようではあるが、自由を最も重んじる米国では、基本的な規格を保存しよう とする傾向が認められる。これは、多民族国家を維持する上で、いつでもどこでも同じよう な規格、同じようなサービスが受けられることをモットーにしようとしてきた結果なのであ ろうか。それは食の文化にも現れている。例えば、マクドナルドのハンバーガーやケンタッ キー・フライドチキンの製法は全米どこでも同じであり、味や香りもほとんど大差はないの は周知の通りである。この傾向は、何もファースト・フードに限ったことではない。ホテル のルームサービスのスパゲッティやクラブハウスサンドイッチ、サラダなどは米国中どこの ホテルやレストランでも大差はないのが実情である。 翻って日本の状況を見ると、そば屋一つをとってもそれぞれのそば屋で、そばの打ち方か ら、つゆの作り方まで一定のレシピに則って作るわけではなく、その味は千差万別である。 近年この傾向はラーメン屋に顕著に現れている。独自に作成した門外不出の秘伝のタレをも とに作成されたラーメンの味、麺の太さや固さは個々の店で異なり、その結果は長蛇の行列 が出来る店と閑古鳥が鳴く店とをもたらす。こうした傾向は食の文化に関わらず、居住空間 や教育システム、さらには文房具や週刊誌などの多様性を生み出している。 個々の個性を重んじる米国が、日常生活における多様性が少なく、逆に没個性を重視し協 調性を優先してきた日本が、食や住などの独自の文化領域において、あらゆるジャンルの多 様性を生み出していることは興味深い。研究手法という点から見た場合、果たして規格化さ れ、類似の膨大なデータから生まれた研究成果の上に立脚した客観性を何よりも大切にした 現在の手法こそが、真実を解き明かすための最良の方策なのであろうか。個性的である為に は絶えず他人と比較することが必要であり、他人の成果がインターネットなどを通じ瞬時に 入手できるようになった現在、米国において確立された他との相互比較の中より生まれてく るサイエンスが、果たして自然界を正確に反映し、その中に秘められた真実を解き明かすの であろうか。膨大な他人のデータに気をとられ、自身の直感から得た感覚的創造物の重要性 を放棄した場合、そこに真実は見出されるのであろうか。 大量消費社会を生み出す上では、画一化した方向性がその牽引車となることは言うまでも ないが、個人個人の成長を生み出さねばならないこれからの社会においては、他人の言動に 振り回されない個人の直感レベルの向上がより重要な要素となるものと考えられる。こうし た「直感」は五感の上に成立するものであり、この五感を研ぎ澄ましてものごとに対処する ことが必須である。ハード部分が米国に匹敵してきた現在、ソフト面での医療および研究が 本邦において大きく飛躍するためには、我々に内在する独自の感性を磨き、個々の患者の状 態や実験結果をより詳細に観察し、その中に秘められた言葉を読み取ることがより大切であ り、そこでは「文献からではなく現場から学ぶ」姿勢、「知識」より「直感」が優先される ことになろう。こうした「直感」から芽生えた日本独自の方向性に期待したい。
弔辞(2003年2月9日、平成15年度 同門会誌)
木村先生、先生がこの世界から旅立たれたことが、未だに信じられない気持ちでおります。 この場にこうしておりましても、「高橋君」と先生からまたお声がかかるのではないかと感 じております。先月1月18日の夕刻、大学の本部棟で行われました同門会の幹事会で先生 のお姿を拝見致しました際、若干お疲れのご様子ではありましたが、出された和菓子を残さ ずお食べになられ、ご一緒にエレベーターで玄館まで参りました時には、まさかこのような ことが起こるとは夢にも思いませんでした。 先生に初めてお会い致しましたのは、入学試験の面接の時でした。偶然にも先生が私の面 接を担当され、「他にどこを受験したの」、「待っているからね。」と優しい言葉をかけて戴い たことを今でもはっきりと覚えております。大学を卒業し、第三内科での研修後、医局長の 薦めもあって大学院に進むこととなり、研修中に免疫学に興味を覚えた私は、再び先生の面 接を受けることになりました。「免疫学はこれから重要な学問になるから、しっかりと勉強 しておきなさい。」、「教室で待っているから。」と、にこやかな口調でお話をうかがい、先生 の暖かく包容力に富むお人柄を再確認した次第です。 先生は昭和47年7月より昭和55年9月までの6年間学長を勤められました。それから昭 和60年3月に退職されるまでのおよそ4年半、ご自分が最も愛された微生物学免疫学教室 に戻られ、教室員ならびに大学院生の教育にあたられました。私が大学院生として実際に先 生のもとで勉強させて戴いたのが、昭和56年の夏頃から昭和60年3月ですから、ちょうど 最後の大学院生として先生にご指導を戴くことができました。楽しかった大学院生活も終わり、私は自分が所属していた第三内科に戻ろうとした時、法 人の常務理事になられた先生は「教室に残る気はないか」、「今すぐに返事をすることはない。 待っているから。」と有り難いお言葉をかけて下さいました。その後、数年間にわたり色々 と悩んだ末、米国留学を経て、結局は先生が主宰されていた教室に戻ってくることとなりま した。先生は決して無理はおっしゃらず、いつも相手の立場を深く考えて、ご助言を下さい ました。考えてみますと、私はいつも先生の手の中におり、先生の愛に包まれることによっ てここまで成長することができたように思います。 今、教室を主宰するようになり、先生がなされてきたご苦労の一端を感じ取れるようにな るにつれ、先生の偉大さを改めて実感する次第です。研究というのは、ともすれば個人的な 業績を追い求めることになり、他人の労力を利用する傾向を帯びる利己的な要素を含んでお ります。先生は、自分の損得ではなく、相手の将来の成長を願う形で、教室員や大学院生を 育ててこられました。その結果、本日ここにお集まりの方々のように多くの素晴らしい方々 を、教室から輩出されました。先生は他への愛を注ぐことが、結局は自らをより多くの愛に 包まれた世界へ導いていくということを、私たちに身をもってお示し下さいました。先生の 人格に触れることができ、私は幸せでした。木村先生、本当にこれまでどうも有り難うござ いました。どうか安らかにおやすみ下さい。